こんにちは。今回は猫好きで有名な作家大佛次郎の「猫のいる日々」を読んでみました。
大佛次郎の家には、常に10匹以上の猫がいて、大佛曰く、猫は「趣味ではなく生活になくてはならない優しい伴侶になっている」。
旅先での滞在が長くなると、猫が恋しくなって、「猫はいませんか?」と猫のいる家を探したりします。
猫好きという評判が広がると、わざわざ捨てにくる悪い輩もいて、ほとほと困って、猫を捨てる人間を軽蔑するのですが、猫嫌いだった大佛の奥さんは、結婚後、大の猫好きになり、生きている捨て猫を拾ってくるだけではなく、死んだ猫まで拾ってきて庭に埋めることもあったそうです。
「一匹の猫はよい。十五匹は、どう考えてもいかんな。」
猫は増える一方だったので、家の者に「猫が十五匹以上になったら、おれはこの家を猫に譲って、別居する」と申し渡します。
ある日、十六匹いたので、「一匹多いぞ」と奥さんに言うと、「それはお客様です。ご飯を食べたら帰ることになっています」と言います。
通いとなったこの猫は、ある日子猫を連れてきて、親子で住み込みに昇格しました。
住み込みの猫、通いの猫、関わった猫は500匹以上だそうです。
すべての猫のことを書きたいけれど、それは無理な話なのです。
「一匹の猫はよいが、十五匹は、どう考えてもいかんな」と思いつつも、塀の上にいる野良猫にも面白い由緒や歴史があるのだと一匹の猫に他の猫への思いをダブらせて万感の思いで書くのです。
大佛次郎が500匹以上の猫との暮らしを通して、猫に対して抱いた思いをいくつかご紹介したいと思います。
仕事と猫
「仕事をするのに、猫と本が手元にないといけないらしい。膝に抱いて撫でてやっていると心が遊べるからいいのである。仕事を始めると、人間よりも猫の方が口をきく義務を解かれるだけでも私にはなつかしいし、都合もいい。」
「仕事を始めると極端に無口になり、ほとんど怒りっぽくなっている。そんな時、彼を喜ばせるのは猫だけだった。猫が人間のように口をきかないのが彼の気に入っていた。黙って猫と遊び、けわしくなっている心が幾分かやわらげられるような心持になる。人間の心持を理解する知能を持った犬には、この役はつとめられなかった。猫が人間に冷淡なのが、好きなのである。どんなに幸福そうに見える者も、人間である限りは酔うかごまかさぬ限りは孤独なものだと教えてくれたのも僕の猫である」
シャム猫
「生まれたときは、全身がクリーム色をしているが、育つにつれ耳とか鼻づらとか、尻尾、足のさきなど体の飛び出した部分から感光してくる。その色がカットグラスの焦げ茶色で、チャイニーズ・ブリュウの目の色と、実に見事な色の調和を見せている。感光の度合いは育つにつれ深くなる。こんな不思議な猫はいない。他の猫に比べると野性が強くて、細いくせに筋肉がよく発達し、暴れだしたら人間の力でおさえきれないくらいぶりぶりしてる。
シャム猫が日本猫と混ざると、ときどき、顔だけ面をかぶったように黒いとんでもないものがうまれるから、おかしい。」
西洋における猫と日本における猫の違い
「日本にあって外国にないのが化け猫映画である。日本の猫は不遇である。」
「日本の猫は、都会的社交的であるよりも、田舎猫で、住む家に付属して、箱入り娘の気質であまり外へ出たがらない。外国種のシャム猫などは、その正反対で、家につかず、人に、特にその中の誰かひとりになじんで、他の家人さえ無視する性質があるが、日本の猫は、「家猫」と言われるくらいに、人間よりも家になついている。だから、引っ越しの多い都会人の生活には向かず、猫らしい猫は、田舎の家に住み着いたものに見かけられる。」
「ほかの動物の全部がお釈迦様の臨終を囲んで泣いたと言うのに、猫だけはどこかで日向ぼっこをしていたのか虫を追って遊んでいて考えなかったのか出てこなかったと言って非難されている。お釈迦様の臨終というような重大な瞬間に居合わせなかったことを勝手に人間が猫の落ち度としたのです。としてもこの怠けっぷりは可憐で美しい。」
「ペルシャ猫。イギリス猫。シャム猫。こうした素晴らしい猫が僕の周囲にいると思っている人がいる。いや、まったく自分でもいたらいい、欲しいなと常に心に描いている。少し馬鹿でもよろしい。日本の猫より美しいことは、較べる方が間違っているかもしれない。
これは負け惜しみといわれるかも知れない。しかし今私の身辺にいる二匹。ー 匹と言いたくないほどに彼らは私の家族の一員だ。
コトンとシロ。純白でなんと立派な体をしていることだ。
日本の猫でも、これを人間同様の生活習慣に入らせ、ネズミを捕ることにも酷使せず、或る程度の贅沢、傲慢を許すならば、決して外国の猫後におちるものではない。」
まとめ
人には、自己と他という存在がありますが、猫には、もしかしたら自己の存在しかなく、「他」がないのかもしれない。
それくらい孤高なのかもしれない。
猫のそういうところにいつの時代の人も魅せられるのでしょう。




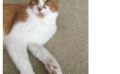
コメント